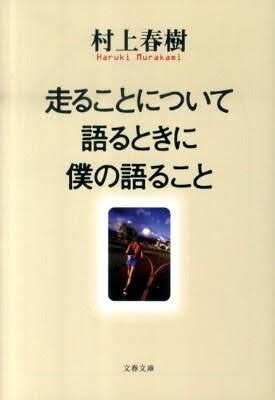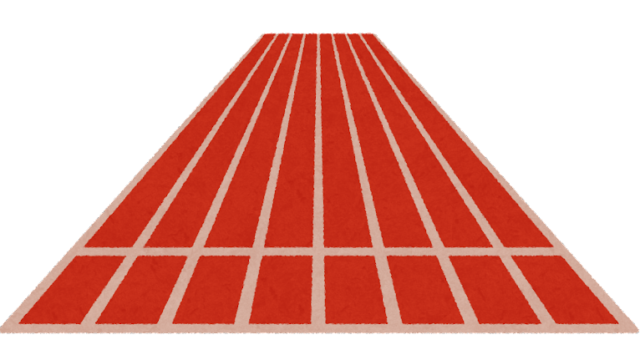ランナーの方に質問です。
『走ることについて語るときに僕の語ること』(村上春樹/著)
という本をご存知ですか?
村上春樹といえば国内に限らず海外からも高い評価を受ける、日本を代表する小説家のひとり。
その一方で、35年以上のランニング歴を誇るランナーでもあります。
そんな村上春樹氏がランニングを軸に綴ったメモワール(個人史)、それが『走ることについて語るときに僕の語ること』。
この記事では、その本から学んだランニングやマラソンの継続に役立つ3つのコツを紹介します。
- 気持ち良いと感じたところで走り終える
- 走る理由を大事にする
- 他人をモチベーションにしない
自身、ランニングを10年以上続ける市民ランナーです。
この1冊に出会えたおかげで、ランニングを辞めずに続けられました。
- ランニングを始めてみたけどうまく続かない……
- ランニングに興味があるけど三日坊主にならないか心配……
上記の悩みをもつ方は、ぜひランナーの大先輩の作品から継続のヒントを学んでいきましょう!
村上春樹というランナー
「村上春樹」というランナーの実力について、詳しく知っていたほうが響く言葉も多いはず。
ランニングの経歴や、走る理由について先に説明します。
ランニングの経歴(参加大会やタイムなど)
『走ることについて語るときに僕の語ること』の内容をもとに、村上春樹氏のランニング歴を以下にまとめました。
- 1982年の秋、33歳のときにランニングをスタート
(「専業小説家」として活動し始めた頃とほぼ同時期)
- 1983年、ギリシャにて初フルマラソン完走を達成
(大会参加ではなく個人での挑戦)
- 1983〜2007年までの間にフルマラソン大会へ25回出場
(年1回はフルマラソンに参加している計算)
- その多くでフルマラソン4時間切り、通称サブ4を達成
(フルマラソン3時間半切りのサブ3.5もクリア)
- サロマ湖100キロウルトラマラソン完走やトライアスロンも経験
大会に参加したことがある市民ランナーは多いと思います。
ですが25年以上、毎年フルマラソンに挑んでいる強者は珍しいはず。
小説を書くにしろマラソンを続けるにしろ、圧倒的な継続力が必要になるのは明らかです。
まさに村上春樹氏は「継続のプロ」と呼べる存在ですね。
走る理由
走る理由について、正確にはそのきっかけとなった事柄を説明します。
作中、このように述べられていました。
ところで、専業小説家になったばかりの僕がまず直面した深刻な問題は、体調の維持だった。(中略)これからの長い人生を小説家として送っていくつもりなら、体力を維持しつつ、体重を適正に保つための方法を見つけなくてはならない。
村上春樹 著『走ることについて語るときに僕の語ること』(文藝春秋 2010年)pp.56-57.
小説を書くための「コンディション維持」が目的だったとのこと。
自分も仕事や遊びを満喫するには体力が欠かせないと感じているため、内容にかなり共感しました。
ランニング&マラソン継続の3つのコツ
それでは本題に入っていきましょう。
『走ることについて語るときに僕の語ること』から学んだ、ランニング&マラソン継続に役立つ3つのコツを紹介します。
1|気持ち良いと感じたところで走り終える
1つ目のコツが、「気持ち良い」と感じたところで走り終えるという考え方です。
村上春樹氏はこのように述べています。
速く走りたいと感じればそれなりにスピードも出すが、たとえペースを上げてもその時間を短くし、身体が今感じている気持ちの良さをそのまま明日に持ち越すように心がける。長編小説を書いているときと同じ要領だ。もっと書き続けられそうなところで、思い切って筆を置く。そうすれば翌日の作業のとりかかりが楽になる。
村上春樹 著『走ることについて語るときに僕の語ること』(文藝春秋 2010年)pp.17-18.
ランニングが長続きせず、三日坊主で終わっては無理やり気合いを入れて走り直していた自分。
試しに文章の方法で走ってみると、以下のメリットが得られました。
- もっと走りたいという欲をキープできる
- 疲労が溜まりにくくコンディションが安定する
翌日のランニングに対する心理的、身体的なハードルを下げることに成功。
継続が楽になった結果、気づけば10年以上ランニングが続いています。
ランニング初心者の方がランを習慣化するための手段としておすすめの思考法です。
あえて余力を残すことミソなんですね。
2|走る理由を大事にする
2つ目に紹介するコツが、「走る理由」を大事にする考えです。
もし忙しいからというだけで走るのをやめたら、間違いなく一生走れなくなってしまう。走り続けるための理由はほんの少ししかないけれど、走るのをやめるための理由なら大型トラックいっぱいぶんはあるからだ。僕らにできるのは、その「ほんの少しの理由」をひとつひとつ大事に磨き続けることだけだ。
村上春樹 著『走ることについて語るときに僕の語ること』(文藝春秋 2010年)p.111.
自身、仕事で忙しかったり疲れたりした日は、それを言い訳にランニングを休んでいました。
そんなとき「走る理由」を大事にしよう、という前向きなメッセージに出会い、ランニングに対する意識が変化。
走れない原因を考え、解決に向けて積極的に行動するようになりました。
- 仕事で帰りが遅くなってからだと走る気が起きない……
- 解決策|時間を安定して確保するために朝ランを開始
- 寒い季節は外を走る気になれない……
- 解決策|防寒用アイテムを用意する、またはジムを活用する
- 走れてはいるけどモチベーションが湧かない……
- 解決策|ランニングノートを書いて成長を可視化する
これらの行動を実施したおかげで、ランニングを始めた頃の目標であったフルマラソン完走やサブ4達成をクリア。
「できない理由」は必ず存在するので、解決策を考えることが大事です。
3|他人をモチベーションにしない
最後、3つ目に紹介するコツが「他人」をモチベーションにしないという考え方です。
「あいつには負けたくない」というようなモチベーションで走る人も中にはいるかもしれないし、それはそれで練習の励みにはなるだろう。しかしもし仮に特定のライバルが何かの事情でそのレースに参加できなくなり、その結果レースを走るためのモチベーションが消滅(あるいは半減)してしまった、というのではランナーとして長くはやっていけない。
村上春樹 著『走ることについて語るときに僕の語ること』(文藝春秋 2010年)p.24.
自分自身、思い当たる節が多くハッとさせられる言葉でした。
というのも、ランニングのタイムや練習量をほかのランナーと比べまくっていたからです。
- 相手にモチベーションが左右される
- 焦りから無茶な練習をおこないケガをする
そんなミスを連発。
しかしこの言葉がきっかけとなり、ランニングへの向き合い方を見直せました。
自分なりの納得感や達成感を重視した、自分軸のランニングスタイルへと転向。
マイペースで走れるようになったおかげで足のケガも減り、10年経った今でも健康にランを楽しめています。
他者に依存しない独自のモチベーションを見つけましょう。
走り続けてよかったこと
ランニング継続によって得られるものは、コンディション維持だけに留まりません。
手に入るさまざまな魅力について知っていると、やる気も湧いてくるというもの。
補足として、自身が走り続けて感じたメリットをいくつか紹介します。
- ストレス解消になる
ランニングによる日光浴とリズム運動のおかげで、「幸せホルモン」と呼ばれるセロトニンの分泌量が増える。
- 成長の手応えが得やすい
マラソンは個人種目であるため、積み上げた努力が結果にダイレクトに反映されやすい。
マラソン大会などの腕試しの場が存在する点もgood。
- 人間関係が広がった
ランニングを趣味や習慣にしている人は多く、そこから新たな友人ができた。
さらに老若男女を問わずに楽しめるスポーツであるため、知り合える人間の間口が広い点も魅力。
本の内容を活かしつつ、得られるメリットを具体的に意識するとより継続しやすいと思います。
よろしければ参考にしてみてください。
まとめ
この記事では『走ることについて語るときに僕の語ること』(村上春樹/著)のなかから、ランニングやマラソン継続に役立つ3つのコツを紹介してきました。
- 「気持ち良い」と感じたところで走り終える(余裕を残すことで取り組みが長続きするマジック)
- 「走る理由」を大事にする(走れない理由があっても前向きに問題を解決していこう)
- 「他人」をモチベーションにしない(相手に依存しない独自のモチベーションを見つけよう)
ランニングが続かずに悩んでいるランナーは、村上春樹氏の考えを活かすことで継続が楽になるはずです。
ぜひ自身のランニングに応用してみてください。
紹介した『走ることについて語るときに僕の語ること』はメモワール(個人史)であり、ランニングのハウツー本ではありません。
ですが個人的には、すべてのランナーにおすすめな一冊。
- ランニング初心者は「なるほど~!」と学びになる
- ランニング経験者は「その気持ち分かる!」と共感を楽しめる
気になった方は、ぜひ一度読んでみてくださいね。
PS.
本を読む時間がない方は、ながら聴きがおこなえるオーディオブックサービス「Audible(オーディブル)」がおすすめ。
今なら30日間無料で聴き放題が試せちゃいます。(2024年2月2日時点)
興味のある方はぜひこの機会に『走ることについて語るときに僕の語ること』をお得に楽しんじゃいましょう!